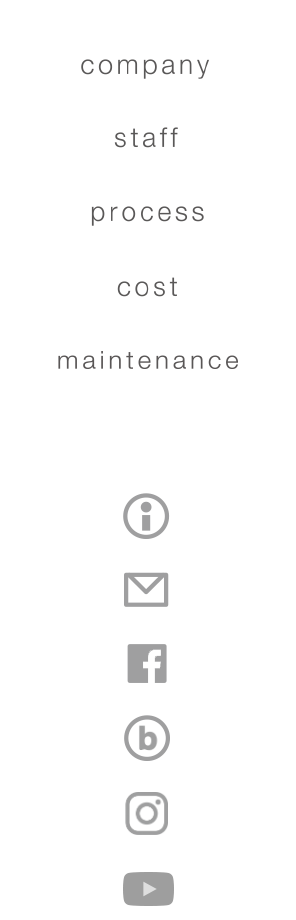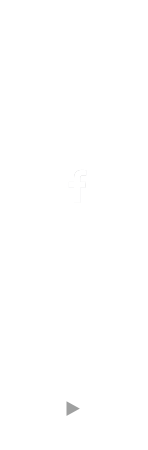(13) 家での暮らしかた・家の使いかた
暮らしかたはいろいろと変化していきます。たとえば出産。子供ができると暮らしかたはがらっと変わります。そして、子供は成長するので、その成長段階によっても暮らしかたは変化していきます。
ペットを飼い始めることによっても暮らしかたや使いかたが大きく変わることもあります。
新たに出会った趣味や出来事によっても変わります。
人生100年といわれるなか、その間には、たくさんの家での暮らしかたや家の使いかたが変化します。
その変化に、さっと対応できる家がやはりいいのではと思います。
新築入居時に「完成」させる必要はありません。住んで暮らして使っていくうちに、いろいろなことを思います。考えます。
暮らしやすい家、使い勝手のいい家、はそのときに応じて、考える余地があったり、実際に工夫することができるような家。
使い慣れた道具のように手に馴染み、そこに想いや記憶も、くっついていくような家やお店は、必ずや、素敵に育っていきます。
(14) ヴィンテージ・アンティーク
もともとはワインの価値を示す用語だそうです。製造されてから、30年~100年未満をヴィンテージ。100年以上をアンティーク。時間をかけて良さが増した品物という意味合いから、ファッションやインテリア、車などにも使われている言葉ですよね。
自分も大好きです。しっかり作った家が、お店が、時間をかけて良さが増していくなんて、素晴らしいことです。もちろんある程度のお手入れは必要ですが、風化によって自然にこなれてゆく様や、住まい手、使い手によって、よりそのらしさがにじみ出ていく様は、本当に素敵なものです。
現在の日本、新築時からの平均建替えサイクルは35年といわれています。築後完成した時が100%で、35年で、ほぼ0%の魅力になってしまう家やお店を作ることは、やはりおかしいと思います。
品番のない本物の素材、シンプルな素材、シンプルな工法・構造、メンテナンスできる身近な素材。親しみやすいサイズ感。流行り廃りのないデザイン。これらを一生懸命考え、本物の素材を使ってあげれば、ヴィンテージ・アンティークとなるべく、家や店を建築することは、さほど難しいことではないと思っています。
(15) 建築物はまちの要素
「まちづくりに関した仕事をしたい」と学生の終わりに思いました。どうすればそれができるのかよくわからず、地元の工務店で働かせていただいて、そのときに、現場監督補助として、商店街のなかのあるお店の新築工事に携わりました。そこで、「あ、建築物はまちを構成する要素なんだ!」と気が付いてから、建築にどっぷりとハマっていきました。
自分の資金でつくるのだから、自分たちだけ良ければいい、という気持ちで家やお店を建てることは、あまりよろしくないように思います。
あの角のお家ってなんかいいよね! とか、お庭の木に花が咲いたね! とか、あそこの洋服屋さんの建物の雰囲気いいよね、あのパン屋さんの雰囲気も好き、とか、そんな会話の生まれる、散歩に出かけたくなるまちになって欲しい。
お店を計画する際は、とくに気を付けるように考えているつもりです。もちろん看板はあったほうがわかりやすいですが、主張の大きすぎる必要以上に大きな看板は、そこに用のない人にとっては邪魔に感じてしまうかもしれません。
近くに暮らす方や、通りを通る人にとってもよろこばれる建築が、お店や商売の品位にも関わってくるものだと思います。
(16) 地場工務店について
昨今の定義とすると、住宅の供給棟数が年間20棟未満の会社のことを工務店、それ以上をビルダー、ハウスメーカーと、順に大規模化していきます。イシハラスタイルは年間6~7棟の供給棟数なので、工務店に分類されます。工務店と一口にいっても、いろいろなかたちがありまして、設計は外注し、大工さんを数名抱えて自社他社の施工をメインにする会社さんもあれば、土地を仕入れて分譲住宅をメインにする会社さん、その業務内容はさまざまで、工務店経営を安定化するために、さまざまなバランスで形態を成り立たせています。
建築の影響はとても裾野が広いものです。自然のこと、子供たちのこと、地域のこと、、、。
少なくとも私たちの日常業務では、家を売っている感覚はありません。○○さんの家や△△さんのお店をつくっている感覚です。地元で生まれ育ち、事務所の隣に住み、日用品を買い物に行けば知り合いに会います。
転勤も人事異動もありません。スタッフの皆も同じようなもので、一緒に協働してくれている職人さんたちもそうです。
下手な仕事はできるはずもなく、大袈裟かもしれませんが、生涯をかけて、お仕事をさせていただいています。お施主さんから、建築資金という大金を預かり、同じような気持ちの職人さんたちに、代わってお支払いをする。職人さんたちの子供さんの顔も知っていたり、お父さんの代から繋がっていることも。多くの地場工務店さんは同じような気持ちでお仕事をされていると思っています。
地場工務店は、一軒一軒、真剣に向き合って建築をしています。
(17) お金の使いかた 伝えかた
子どものころ、学校帰りに寄り道していたいくつかの駄菓子屋さんや文房具屋さんは、今、ほとんど無くなってしまいました。夏休みにはアイスキャンディーを買ったり、ときにはお店のばあちゃんに叱られたり励まされたり。近所の八百屋さんや肉屋さん、魚屋さんなどの個人商店も少なくなりました。どのお店も、たとえ小さなお買い物でも、やさしい挨拶をいただき、心からのありがとうの言葉をいただきました。
日常の一瞬のことなのに、なにかと記憶に残っているものですが、あるとき、あそこのお店も閉めてしまった、ここのお店も無くなってしまった、と少し寂しい気持ちになった際に、「ガツン」と衝撃が走りました。これは自分たちがいけなかったのでは!? と。
駐車場が広く営業時間の長いコンビニやスーパーマーケット、さまざまなものが自宅で購入できるネット通販。時代の流れや文明、技術の開発により、どんどん便利になっていく日々。新しいから、便利だからとついついこのような買い物のしかたをしてしまっているからなのでは、と。
新しい仕組みや技術、便利になることは歓迎すべきことです。ただ、お金を使うということはモノやサービスをその対価を支払って手に入れることですが、お金をつかうその先には、モノやサービスを提供してくれる人がいて、そのお金がどのように伝わっていくのかということを意識して使うことも大事なことなのではないか。そんなお金の使いかたを心掛けたいと思いました。
わたくしの個人的なお金の使いかただけでなく、仕事のうえでも、お客様から預かった工事代金で材料を購入したり、各職人さんや工事店に費用を支払うときに、大切なお金がどう伝わっていくのかをちゃんと意識していくことを心掛けます。そして、家づくりを依頼していただいたお客様に、心からのありがとうという気持ちを伝えていけたらと思っています。
(18) 縄文の暮らし
幼少期のころ、家族旅行で静岡県の登呂遺跡に連れて行ってもらいました。弥生時代の暮らしの展示や再現建物があり、なぜだかとても興奮した記憶があります。(今思えばここから繋がっているのですね)
学生時代の好きな科目は地理でした。古くからある集落は、そこに存在していた理由の大半は地理地形によるものです。地図帳をながめ、その暮らしを想像すると、そこでの四季の暮らしや、その立地の自然はどうなのか、それがどう発展・衰退していったのか。そんなこんなで、大学では地理学専修で学ばせてもらいました。そこから、まちづくり、建築へと転じ、今のお仕事とさせてもらっています。
縄文時代の暮らしは、個人的に、とても興味を持っています。
縄文時代は1万年以上続いたとされ、とても豊かな暮らしをしていたようです。日本独自の文化であり、争いの少ない平和な時代だったそうです。気候も良く、森にも海にもたくさんの食料があり、春には山菜、夏は漁労、秋は木の実、冬は狩猟という、季節変化に応じた計画的な労働(縄文カレンダー)での暮らしがありました。
おもな男の仕事は狩猟だったり、船作り、石器作り。女の仕事は木の実や貝拾いや土器作り。ムラで協働で畑をつくり、竪穴住居も協働で建造。狩猟の相棒として犬を大切に飼っていたようです。
1万年以上続いた縄文のDNAは、必ず現代でも引き継がれていると思います。だから女性は竹籠(かばん)が好きなんだ、だから男性はつるつるの石が落ちていると拾ってしまうんだ(狩猟用石器)、などなど、勝手になのですが思うことがたくさんあります。
竪穴住居は、地面を少し掘りくぼめて床とし、柱を4~7本建て、煙り出しのある(茅葺き)屋根を掛け、中央には火をたく炉、という形式です。あれ? 日本各地の山間部ではこの縄文の建築技術はつい最近まで続いていたよね? というくらい脈々と繋がっています。
縄文の暮らしに戻ろうとしているわけではありませんが、DNAに刻まれているであろう、すばらしい文化、人間愛、自然愛、幸福さや心地よさの基準を、素直に受け入れる。この縄文から続く変わらないもののなかには、素敵な家づくりやお店づくりのヒントがたくさんあると思います。