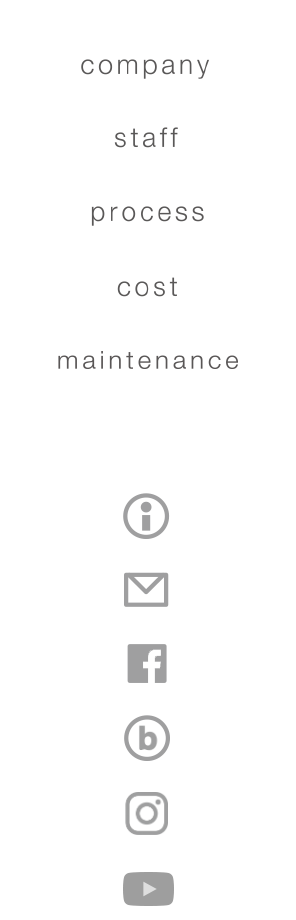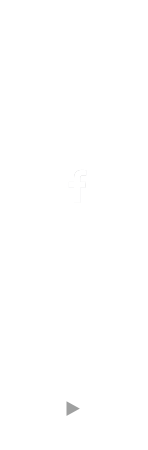(7) ペットや動物
わが家には、大型犬1匹とにわとり(烏骨鶏)2羽がおります。以前飼っていたこともある、猫もインコも大好きです。命を預かり、一緒に暮らしていくことは、お世話が欠かせず手間の掛かることです。手間の掛かることは、やはり、豊かさにも繋がっているなと感じます。
ペットたちは、虫や植物の生命力に加えて脳を持っています。ときに無条件に愛を求めてきて、ときに相手にもしてくれず、その自由なさまを見ると、自分たちの人生観をも顧みたりするほどです。
大半のペットたちは私たちより寿命が短く、そして、私たちが暮らす「家」というものを「巣」「仲間」と認識して暮らしています。
先日、建築後数年経たお客さまのお宅に行った際、かわいいやんちゃな子犬が元気に走り回ってました。
「もう、ほんとに大変で、、」なんておっしゃりながらも、自分も笑顔に、子供さんたちもみんな笑顔でおられました。
建築する際に、ペット共存の計画をさせていただくこともありますが、何らかのご縁やタイミングで飼うことになったっていうのもいいですよね。
なにか困ったことがあれば、一緒になって知恵を絞り、お家をカスタムしたりして、人も家族もペットも一緒に暮らしていく様子は、自分にとっても、幸せな気持ちと笑顔を与えてくれます。ぜひご協力させてもらいたいものです。
(8) 薪ストーブ
20年ほど前に自宅を建てた際、薪ストーブを導入したいな、と考えていました。しかし、薪の調達、メンテナンス、忙しい日々の生活、導入コスト、などに躊躇し、新築時には導入することを見送りました。
20年ほどの月日を経て、後付けで、昨年導入することができました(事務所棟にですが)。
ストーブ性能の向上で、針葉樹を燃やすことも問題なく、燃費も向上しており、メンテナンスや設置スペースも、かなり融通がきくものがありました。
薪の準備をしたり、灰の掃除、火を付けたり、薪を足したり。ボタン一つで暖かくなるエアコンとくらべたら格段に手間の掛かる作業なのですが、不思議と全くといっていいほど苦にはなりません。
遠赤外線の暖かさはもちろん気持ちの良いものなのですが、少しの手間が掛かることはやはり大切なこと、豊かさにつながるものだなと実感しました。
新築時に計画できるのはベストではありますが、自分たちのように、人生のタイミングをみて導入することも可能です。
ストーブを焚かない季節には、ちょっぴり冬が待ち遠しくも感じます。季節に応じてやることがある。これってなかなかいいものです。
(9) 家の寿命
イシハラスタイルでつくる家の寿命は、新築~80年ほどがよいのではないか、と考えております。現代の日本の建替えサイクルの平均は35年といわれているので、倍以上の年数設定となります。80年という設定の理由は、まずは鉄筋コンクリート基礎です。現代日本の木造建築の大半の基礎は、鉄筋コンクリートでつくられます。イシハラスタイルでつくる基礎も鉄筋コンクリートです。気象条件や立地条件にも左右されますが、実はコンクリートにも寿命があるのです。
コンクリートは、空気中の二酸化炭素の作用を受け、時間とともにアルカリ性が低下。そうすると内部の鉄筋が錆びて膨張し、ひび割れなどを引き起こしコンクリート内部がさらに劣化します。この中性化の速度などを考えると、~100年程度となります。
基礎だけを作り直すなど、いろいろ補強工事として出来ることはありますが、費用がかさむのと、ほかの部分の具合も想像すると、80年くらいが妥当ではないかと考えます。
柱や梁の構造材の木材は、まだまだ使えるとは思います。しかし、給排水管、電線など、設備的な素材の寿命もあります。これらも途中のどこかで更新することが必要かもしれません。外壁や屋根のメンテナンスや取替などの更新も途中で必要になります。
(これらの更新のタイミングや費用、それらをまとめたことも、イシハラスタイルが開催する家づくり勉強会でお話ししています)
今お話ししていることは、いわばハード面(コンクリートなどの構造の素材)のことですが、80年という年月をどう経ていこうかと考えると、ソフト面(間取りや暮らしかた)のことも重要です。その時代、年齢に応じた暮らしができるシンプルな間取りであること。適切な大きさであること(大きな家はメンテナンス費用も多大となります)。改修工事やメンテナンスがしやすい素材であること。
木造住宅で使う、国産材の杉や桧の材は、50~80年生のものを伐採して使います。おじいちゃんたちの世代、山で育ってくれた木々に、感謝の意を込めて、せめて同じくらいの年月は使っていってあげたいものです。
(10) 記憶
しっかりと記憶が刻まれていく建物はとても良いと思います。わかりやすい事例としては童謡の「背くらべ」。柱の傷は一昨年の~です。このシーンは物理的にも、本物の木の柱が見えてないとできないですね。
梁が出ていると子供は柱を伝ってぶらさがり、滑って落ちてべそをかいたりします。吹抜けがあれば何か物を落としてみようと思って叱られたり、きれいな壁があれば落書きをします。犬を室内で飼えば柱の角をかじってみたり、猫は壁で爪を研ぎだし、カーテンを引っ搔きます。
家の傷は思い出に繋がります。いずれ時がたつと、その記憶が、親も子も、家族の幸せな話題となります。
そこでなのですが、その傷の相手が重要なのです。往々にして自然素材(木や土。鉄や石や布も)であれば、その傷を受け入れてくれます。新建材と呼ばれるものは、なかなか受け入れてくれません。自然素材にできた傷は、自分たちでも補修もできます。気楽な素材だからです。同じ白い室内の壁の経年変化を比べてみても、ビニールクロスの壁と漆喰壁ではやはり違いますよね。
傷ではなくとも、記憶されるシーン(場面)もあります。夏休みにあの押入れのなかで基地をつくってみたよな、蝉の声と暑さとあの匂い、、、」「じいちゃんはあの縁側でよくウトウトしてたよな」「姉ちゃんはここで音楽を毎日聴いていたよな」「カレーライスの匂いが好きだったな」
家族の笑い声やときには涙した思い出。日々暮らしているだけでさまざまなことがあり、その記憶は家とともに刻まれます。
演劇やドラマ、映画に例えてもわかりやすそうですね。演者さんは家族やペットで、照明は陽の光、音響は風の音や日常の音、舞台セットが家。
しっかりと記憶がその家に染み付き、自分の居場所はこの家であり、最後の最後まで記憶と共にここで暮らしたい。そんなふうに記憶が刻まれていく建物を、一緒にお手伝いできたらと思っています。
(11) 五感について
視覚・聴覚・触覚・嗅覚・味覚のことを五感といいますが、情報判断の80%以上が視覚とされています。確かに建築物の案内も、WEBや雑誌などの写真によるものであったり、自分たちが見ていいなあと感じるものも視覚からが大半です。しかし、実際にその家で暮らしてみると、視覚以外の、聴覚(聞こえるもの)・触覚(触れるもの)・嗅覚(匂うもの)・味覚(味わうもの)も同じくらいの重要性があると感じます。
風や雨の音、鳥の声などの自然な音。家族の足音や洗い物、近所の犬の鳴き声などの生活音。
あまりにうるさく感じるものはどうかとおもいますが、自然の音や生活音は、集中力を増したり落ち着いたりします。
触れるものもとしては、床の感触や座った時の感触、玄関のドアノブの感触、浴槽の感覚。触れるものはやはり自然素材が気持ち良いものです。
匂うものも重要。朝パンが焼きあがった匂いや味噌汁の匂い。晩御飯のおかずを子供と予想。木がふんだんに使われている家では、洋服に匂いが染み付いて、木の匂いがするよと言われてしまうこともあります。お風呂に桧の板を少し使ってあげるだけで、毎晩心地よい入浴タイム。
味覚はキッチン。業務用ガスオーブンでの料理はおいしくできること間違いなしです。
毎日の暮らし。五感が働く家やお店は、心身ともに健全で、とても魅力的な建物といえます。
(12) 好きな建物
イシハラスタイルでは工事をさせていただいた物件を「お家を見せてもらう日」として、見学会を開催しています。住まい手のかたの完全なるご厚意です。そこにはイシハラスタイルで以前建てていただいたOBさまが顔を出してくださることも多いです。その際には、「気持ちいいお家ですね」「素敵なお家ですね」「あ、こういう場所いいなぁ」「あ、これは自分のとこにはないなぁ」など、いろいろな感想を教えてくれます。
しかし、やっぱり自分の家が一番好き、というようなことを言ってくださいます。
私自身、建築をライフワークとし日々向き合っているつもりで、機会があれば、全国各地の素敵な建築を見たり感じたりするために出かけることがあります。
土地の読み込み、サイズ、素材感、雰囲気や空気感、と高いレベルでまとまった建築を感じると、おぉ~素晴らしいと感嘆の声をあげてしまいます。
そしてその出張から自宅に帰ってくると、すぐにスイッチオフになり落ち着きモードです。やはり自宅が一番なのです。
おそらくそれは、明るさ、生活音、匂い、空気感、空間のサイズ、などなど。それに加えて、いつも安心して寝起きできている経験、その暮らしてきた記憶があるからなのでしょう。
たくさんの記憶が刻まれ、普段からあたりまえに五感が癒される家。必ず、「自分にとっては一番好きな建物」が「自宅」になると思います。