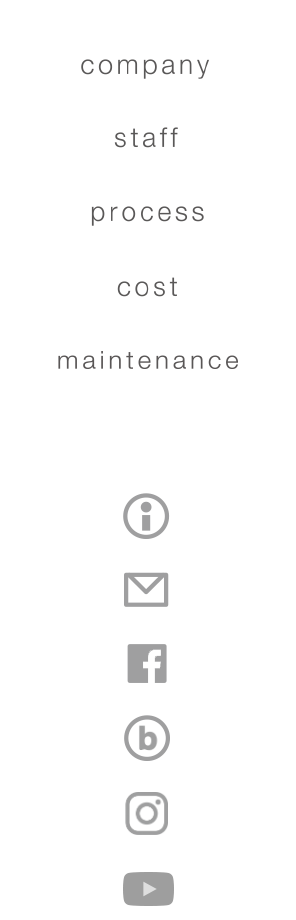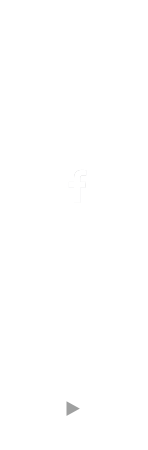家の仕様だけでは計れないこと
学校を卒業して建築と出会ってから、かれこれ30年近く経とうとしてます。
この間には、いろいろな出来事、それらに対する感情、戸惑い、数々ありました。それでもやはり、私は建築が好きです。
新しく住まう方たち、新しく使う方たちのことを想像し、計画をし、設計をし、木や土に触れながら実際に建物をつくる。そこには、新しい暮らしや人の流れがうまれ、様々な生活が営まれていく。
大きな責任を受け持つ重圧を感じる反面、大きな嬉しさや充足感も生まれる。
私だけでなく、イシハラスタイルのスタッフの皆、関わる業者さん、職人さんも建築が好きで、今までも、これからも、建築に携わって生きてゆくのだと思います。
(1) 水や空気のように
私たちが普段あたりまえに使っている水は、山から流れてきています。私たちが呼吸している空気の中の酸素も、山が大きく関与をしています。森林を構成する一本一本の樹木は、光合成により大気の二酸化炭素を吸収するとともに、酸素を発生させながら成長しています。
都市部で日常生活を送っている私たちは、この当たり前のことを忘れて生活をしています。
日本は国土の7割が森林で、そのうち約5割が天然林(自然の力で生まれ育った天然の森林)、約4割が人工林(木材生産を目的とした、いわば木を収穫するための畑)、約1割が原生林(人が全く立ち入らず長期安定している森林)、という構成です。これらすべての森林は、私たちの生命維持に必須な水や空気を提供してくれています。
人工林では建築用途に適した杉や桧の針葉樹が植林され、草刈り、間伐、枝打ちなど人が周期的にサポートし、管理しながら計画的に育てていきます。50年~80年ほどで収穫(伐採)の時期を迎えることが多いです。
この人工林は、人の手を入れていかないと荒れていきます。荒れた人工林は、光が地面に届かず、栄養が行き届かないひょろひょろの細長い木となり、建物や道具の材料にすることができません。また、生き物が住みにくい森林となり、固くなってしまった土では保水力が低減し、洪水や土砂崩れを引き起こすこともあります。
人の手を入れるためには、山に携わる方々の営みが成り立つことが必要であり、林業を荒廃させないためには、人工林で育てた木(畑で栽培された作物)を建築資材として使っていくことが大切なことではないでしょうか。
日本の、自国の森林資源の使用率は3割程度といわれており、約7割は輸入材ということです。ストックは沢山あります。増えていく一方です。国産材は、あるけど使われていないということです。
毎日自分たちが生きるために必要な水や空気の多くは、おそらく近くの山がお世話してくれています。
感謝の気持ちを抱きつつ、木を使いながら、長い目で見守り、上手に共存できることが、やはり人にとっても山にとっても大切です。
(2) 山のこと、ウッドショック
人が生きるために必須な水や空気は、山が大きな役割を果たしてくれています。10年ほど前でしょうか、人工林を紹介してもらう機会があり、その人工林のなかで、代々働く70歳くらいの林業関係者の方とお話しする機会がありました。「今、あそこの尾根の下あたりの杉を伐採しておるんだけど、あれは俺のじいちゃん達が植林してた杉なんだ」
人工林では伐採して、また、植林します。今私たちが使っている国産材の木々はおじいちゃんたち世代が植えてくれたもので、新しく植林する苗木は、お孫さんの代のための木なんですよね。
私の日々の仕事における時間の概念とは、あまりにもギャップがあり、大変深く、この会話が思い出になっています。
人工林を使う、このサイクルを適切に管理すれば持続可能な資源です。今、使ってあげて植えないと、私たちの孫の世代に森林資源を残すことが難しくなります。
2021年を発端とするウッドショック。いろいろな海外からの要因が重なってはいますが、私たちの日本には豊かな森林資源があるにもかかわらず国産材を上手に使うことができていなかったことも反省すべき点だと考えます。戦後の高度成長期から多くの木材を輸入材に依存した結果、国内林業の順調な発展を支えることができていなかったことです。
いま、私たちができること。それは、これから家を建てるときには、近くの山の木(国産材)を使って建てること、に尽きると思います。
(3) 子供たち、次世代
お客様と打ち合わせするとき、「いま、建てようとしている家は、お隣に座っている可愛いお子さんの実家を建てることです」と、よく言ってしまいます。空気や水、山のこと。親として、大人として、何を考え、どのように選択、決断して家を建てたか。将来、子供たちに、「なんでこの家を、どんな風に建てたの?」と聞かれたときに、恥ずかしくない理由を伝えてあげたい。こっちのほうが安かった、簡単だった、便利そうだった、そもそも考えてもない、なんてことが無いように。
自然のこと、時代背景のこと、人との関わりのこと、いろいろ悩んだこと。大人に比べ圧倒的に子供たちは感受性が豊かです。本物の木や土に触れて育つのと、ビニールにラッピングされた家で育つのとでは、きっと、何らかの違いがあるような気がしています。
そして、その子供たちが大人になり、家をつくる際には、「私は実家が好きです。私の実家のような家を建てたいです」と言ってほしいものです。
(4) 住みやすさとは
日々家をつくっている自分が、この言葉について、勝手に自分で感じている言葉の印象のお話です。住みやすい家と言葉でいうのは簡単ですが、住みやすい家ってなんなのでしょうか。非常にふんわりした言葉で、抽象的だけど、いいイメージの湧く言葉ではありますが。
住みやすい家、と聞いて、まずはなんとなく思いつくのが室内空間での住みやすさの印象でしょうか。
家事動線がよいとか、掃除が楽とか、冬暖かいとか、風通しがよいとか、明るいとか。もちろん、それらは良いに越したことはなく、家をつくる際に大切なことの一つの部分ではあります。
少し整理して考えると、「住みやすさ」という言葉から思い浮かぶことは、大きく二つに分けられると思います。
一つは、時間や労働を少なくできる便利さ。もう一つは、感覚的に感じる気持ちよさ。この二つが混ざっているのかなと思います。
前者の、時間や労働を少なくできる便利さ、については、それによりできた時間や余裕をどう使うのか、使えるのかをイメージすることが重要だと思います。
後者の、感覚的に感じる気持ちよさ、は、家をつくる際に、しっかりとイメージを持って、大切に考えたいことです。
この感覚的に感じる気持ちよさは、きっと裏切りません。頑張って想像して気持ちのよい家を建てましょう。
休日の午後、お庭で音楽をかけながらのんびりと草取りするのもわるくない。通りがかりのご近所のおばあちゃんが声をかけてくれる。子供も適当にそとで遊びだす。そうこうしていたら日が暮れだして、こじんまりと作った菜園のねぎを収穫。晩御飯の薬味にでも使おうか。そういえばたくさん採れたからといただいた玉葱もあったな、と。
もしかしたら、時間や労働を少なくできる便利さの追求は、ほどほどにしておいたほうが、暮らしている実感、を持って暮らしていけるような気がします。
(5) 豊かさ
勝手に自分が感じている言葉の印象のお話です。「豊か」ということは非常にありがたいことです。諸先輩方が身を削って貧しくならないよう築き上げてくれたこの世の中。モノや食料がたくさんあり、文明や技術の発展によりかなえられた生活のうえでの余剰時間、命や危険などの不安を感じずに暮らせる日常、などと、振り返って考えてみれば、本当にありがたいものです。ここでいう「豊かさ」なのですが、そのありがたい豊かな日々の暮らしの中で、さらに感じることがある「豊かさ」のことです。ちゃかちゃかと日々忙しいんだけど、その中でちょっぴり幸せな気持ちを感じてしまうこと。そのような「豊かさ」が感じられるように、自分たちの建築を通して何かできることはないものだろうかと。「このエリアで、普通に暮らし働き、その人たちがちょっぴり豊かな気持ちを感じて暮らしていくこと、とわたしたちが目指す建築、の関係」は、大きなものがあると考えています。
それは「手間が掛からない」の逆方向に「豊かさ」はあるような気がします。
語弊を恐れず逆説的にいえば、「手間が掛かること」が「豊かな気持ちになれる」一つの手段なのかもしれません。
(6) 虫や植物
暮らす地域や場所にもよりますが、虫や雑草にネガティブな印象を持つことは少なくありません。虫や植物は脳をもたず、それらが持つ生命力のままに生きています。やぶ蚊も、「今日はこの方はお疲れそうだから刺すのをやめておこう」なんて考えてくれません。屋内にふと現れる虫も、「今から少しお邪魔します、あ、見つからないようにしておきますんで!」と言ってくれたらワーキャーならずにすむのですが。
雑草も成長時期になると遠慮せずガンガン成長します。せっかく綺麗に草取りしても、数週間でまたボサボサに。だからといって、新築時の計画時点からこれらを排除すべく、コンクリートで土を覆いつくしてしまう計画も私はあまり好みません。
草取りも、ときに、気持ちのリフレッシュになります。虫や植物がないと、野鳥も近寄ってきてくれません。野鳥が寄ってくると、フンに混じった種から新しい芽をだすことがあります。思いもよらない場所に。
草取りなど、この手間が掛かることが豊かな気持ちになれる一つの鍵かもしれません。自然との共存や共生、何かをすればクリアできるなど簡単なものではなく、いい距離感を見つけることが大切なことではないでしょうか。
現代の自分たちの生活と、虫や植物と共存するためのほどよい距離感は、「暮らしていくうちに見つけていく」くらいがいいのでは? と思います。
以前建築させていただいた、山の中にあるような立地のお宅。時期になると、ムカデが毎日のように玄関やサッシ廻り、室内にも現われ、本当に困り果てておられました。住まい手さんと、私たちや庭師さんを交え、いろいろな作戦を練ったうえ、家の周りに遊歩道のようにコンクリートを打設しました。
さて、ほどよい距離感が保たれていますように!