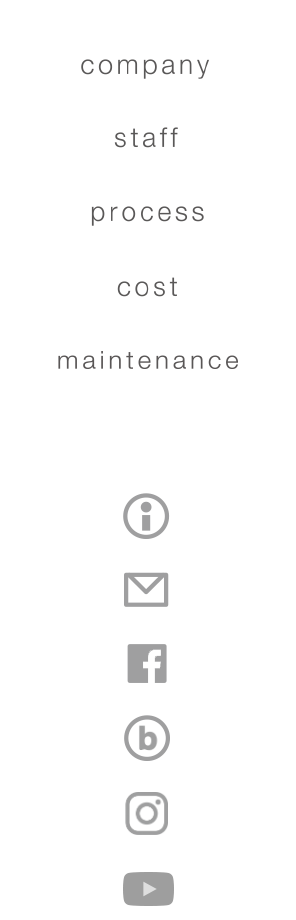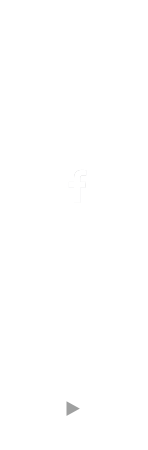家の仕様について
イシハラスタイルの家の仕様について、私の言葉で26項目にわたってご説明します。
お客様一人ひとりの暮らしに合わせてお家のプランはそれぞれですが、「道具のような家」を具現化するため、
わたくしからみてこのようなものがいいのではないか、という材料、工法、構造をまとめております。
住みやすく、快適に、修繕ができ、長く存続可能な家であることを考え続けている中で、
現在ご提案するイシハラスタイルの仕様です。
(7) 屋根材について
よく採用されるのは、ガルバリウム鋼板の屋根です。ガルバリウム鋼板といっても、並のもの(カラー鋼板)と、長期耐久性の良いもの(タイマカラー)とあります。 塗膜の性能がちがいます。弊社ではタイマカラーを使います。色の出方もマットで、町並みや周辺環境に馴染みます。
 ガルバリウム鋼板の屋根は軽いため耐震性に優れ、屋根勾配が緩くても雨水の侵入リスクが少ないので、
建物高さを抑えることができます。素材は薄く、蓄熱することがないため、外部温度に応答した考えで断熱計画をすることができます。
瓦を使用することもあります。三河はとても優秀な三州瓦の産地でもあり、好きな素材でもあります。
ガルバリウム鋼板の屋根は軽いため耐震性に優れ、屋根勾配が緩くても雨水の侵入リスクが少ないので、
建物高さを抑えることができます。素材は薄く、蓄熱することがないため、外部温度に応答した考えで断熱計画をすることができます。
瓦を使用することもあります。三河はとても優秀な三州瓦の産地でもあり、好きな素材でもあります。瓦は長期耐久性に優れ、一枚一枚の交換ができるので、台風などで万一めくれたとしても補修が容易です。 鋼板屋根に比べ重いので、設計には配慮が必要です。いずれの場合も、屋根材の下には通気層を設け、 雨の侵入を防ぎつつ、結露を防ぐ構造としています。
(8)軒について
軒は、広く大きく出す計画とすることが多いです。床面積には反映されず、俗にいう坪単価には反映されません。 軒を大きく出せばコストは上がる方向なので、ローコスト住宅の大半は軒の出は抑えられています。 多少コストがかかっても、広く大きな軒のメリットは沢山あります。風雨から建物を守り、紫外線を遮ります。
このことは、外壁のメンテナンス周期を大きく伸ばしてくれます。
多少コストがかかっても、広く大きな軒のメリットは沢山あります。風雨から建物を守り、紫外線を遮ります。
このことは、外壁のメンテナンス周期を大きく伸ばしてくれます。雨が降っていても窓を開けることができ、風通しが良く、冷房使用を抑えることができます。 雨の日も、強い陽差しの日も、ちょっとした屋外作業ができます。
 住んでみると、軒下はとても使える空間であり、半屋外空間として活躍するでしょう。
軒を大きく出すには、構造材の構成も大きく関わるので、計画段階から検討します。
住んでみると、軒下はとても使える空間であり、半屋外空間として活躍するでしょう。
軒を大きく出すには、構造材の構成も大きく関わるので、計画段階から検討します。
(9)外壁材について
弊社では、大きく三種類の材料のどれかで外壁を計画します。杉板か、ガルバリウム鋼板か、漆喰塗りです。しっかりした軒があり風通しがよい場所では、杉板張りをおすすめします。工業製品のように廃番がなく、 価格を抑えながら雰囲気も良いことが特長です。15㎜ほどの厚さがある木材であり、 熱を遮る効果が高くなります。外壁という垂直面に張るので、水は切れます。悪い環境でなければ、そう簡単には腐るものではありません。 数十年後、風雨や紫外線により劣化が起きても、部分的に取り換えることもがきます。
 「よろい張り」という伝統的な張り方で下から順に板を重ねて張っていくのですが、取替もしやすく、
地震などの揺れの際は、蛇腹のように力を分散させ、外壁の大きな面にクラックをおこすことを防ぎます。
無塗装も可能ですが、木材保護塗料を塗ることが多いです。外壁の杉板は、赤身勝ちのラフ仕上です。
木材の芯に近く、辺材(白身)に比べ耐久性は格段に上がります。表面はザラザラさせ表面積を上げます。
そうすることで木材保護塗料の吸い込みを良くし、さらに耐久性を上げることにつながります。
「よろい張り」という伝統的な張り方で下から順に板を重ねて張っていくのですが、取替もしやすく、
地震などの揺れの際は、蛇腹のように力を分散させ、外壁の大きな面にクラックをおこすことを防ぎます。
無塗装も可能ですが、木材保護塗料を塗ることが多いです。外壁の杉板は、赤身勝ちのラフ仕上です。
木材の芯に近く、辺材(白身)に比べ耐久性は格段に上がります。表面はザラザラさせ表面積を上げます。
そうすることで木材保護塗料の吸い込みを良くし、さらに耐久性を上げることにつながります。
 ガルバリウム鋼板はメンテナンスの心配が少ない素材です。工業製品のため、単調で無表情になりやすいですが、
計画によっては、素朴で良い雰囲気にすることもできます。
ガルバリウム鋼板はメンテナンスの心配が少ない素材です。工業製品のため、単調で無表情になりやすいですが、
計画によっては、素朴で良い雰囲気にすることもできます。漆喰塗りは、大工工事で木摺り下地をつくり、左官工事でラスモルタルの下地をつくり、仕上げに漆喰を塗ります。 下地工程に時間も要し、仕上げ塗りにも左官人数も要します。コストは掛かりますが、メリットも多くあります。 漆喰は耐火性に優れ、強アルカリ性という性質上、有機物を分解する殺菌性があります。 そのため、汚れにも強く、日本の風土に合った材料で、雰囲気も良いです。 いずれの外壁材も、下地には通気層を設け、壁体内結露が無いような仕組みとし、周辺環境やその家の計画により選定していきます。
(10)窓について
木製サッシを計画することが多く、性能も雰囲気もとても良いものです。木製サッシの断熱性能は「最も高いもの」となります。使用ガラスはLow-eペアガラスです。 国内の工場で生産品で、何度も工場に訪問して打ち合わせを重ねてきました。 使用する材料、精度ともに素晴らしいものです。 自宅玄関でも17年以上使っていますが、大きな不都合はありません。
 木製サッシにせよ、アルミサッシにせよ、窓をつけることはコストが掛かり、断熱性能に関しては不利に働きます。
どこかしこも窓をつければよいというものではなく、よくよく考えたうえで、効果的な窓を配置することが肝要です。
木製サッシにせよ、アルミサッシにせよ、窓をつけることはコストが掛かり、断熱性能に関しては不利に働きます。
どこかしこも窓をつければよいというものではなく、よくよく考えたうえで、効果的な窓を配置することが肝要です。窓のない部分である「内壁」は、まとまりを持たせた、きれいな壁をつくることができることにつながります。 風の通り、陽の入り方、間接光の具合、景色の見え方、室内の照度、こうしたことを複合的に考えイメージし、窓を配置します。

(11)床材について
主に杉の厚材を使用します。厚さは30㎜。愛知県東栄町付近から採れる杉材です。伐採に適した季節に木を伐り製材し、丁寧に乾燥させるのでほど良く油分を残した色艶の良い床材となっています。 けっして節のない綺麗なものではありませんが、生活空間と相性良く馴染む材料だと思います。
 サラっと足触りも良く、冷たさを感じず、直接寝転んでも気持ちが良い床になります。節や色むら
があるからこそ、生活に伴う細かい傷や汚れを許容してくれます。
サラっと足触りも良く、冷たさを感じず、直接寝転んでも気持ちが良い床になります。節や色むら
があるからこそ、生活に伴う細かい傷や汚れを許容してくれます。当初は柔らかいのですが、年月が経つと表面が圧縮され、ほど良い硬さに落ち着いてきます。 15㎜の厚さでも十分なのですが、やはり厚板は、素材の持つ力を醸し出します。
杉材のほかに、同じ産地の桧材、輸入材のオークや、松、南洋材などのフローリングを使用することもあります。
(12)内装仕上について
弊社オリジナルの珪藻土塗り(MPパウダー)、EP塗装(水性塗装)、杉や桧の板材、桧合板、ラワン合板、シナ合板、を使います。 雰囲気のお好みや、建物の計画により選定します。珪藻土は、調湿作用に優れ、夏場のエアコン使用がかなり少なくなったという声をいただきます。
機能を持たせた壁としてはとても優秀です。
珪藻土塗りやEP塗装の下地は、石膏ボードに塗ります。石膏ボードは工業製品であり、品質が安定していて、 安価である一方、数十年先も安心できる材料か、と考えると一抹の不安が残ります。 加えて、石膏とうい性質上、ビスや釘を打ち付けても引き抜きの強度はほぼありません。 近代以降、この地方での一般住宅建築では、土壁に仕上げ塗りをする土壁工法の家が多く、「壁はさわるものじゃない」とされていました。 その流れで考えれば、石膏ボードに壁仕上げをすることは、まったく問題のない普通なことではありますが、 もっと気楽に、壁も有効に使っていきたい、という考えの方には木質の内壁にすることをおすすめしています。 杉板や桧合板を張った家は、とても気楽に、きれいに住みこなせます。
 また、杉板にEP 塗装(白系)を現場塗装した壁は、木の質感もあらわれ、白壁の空間に置く家具や調度品もコントラストが効いて、
映え、ほど良くラフであり、ビスや釘も効き、わたくしの好みでは、一番のお気に入りです。
また、杉板にEP 塗装(白系)を現場塗装した壁は、木の質感もあらわれ、白壁の空間に置く家具や調度品もコントラストが効いて、
映え、ほど良くラフであり、ビスや釘も効き、わたくしの好みでは、一番のお気に入りです。