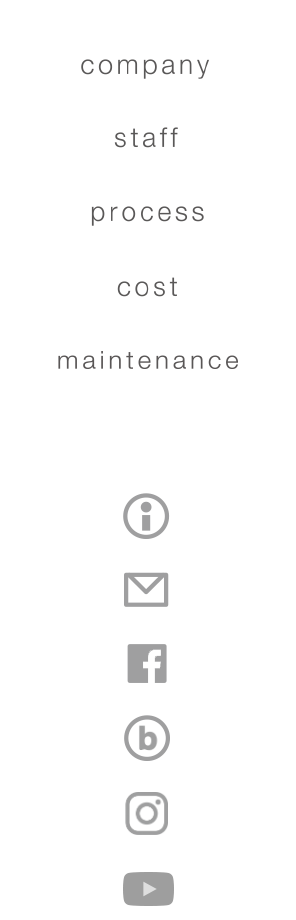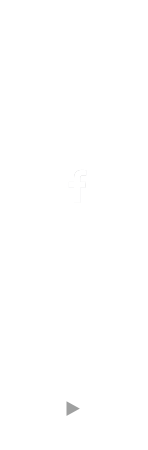家づくりについて
真摯に、丁寧に、棟梁の志を持って。
イシハラスタイルは西尾の工務店です。
地元の職人、地元の素材、地元の植栽。地元を大切にした家づくり。イシハラスタイルは、地元に
暮らす人と共に、地元の工務店として一緒に住まいを考えます。そこに住み、楽しく豊かに生きて
いくために、もっとも重要な基礎の基礎だと信じるからです。
家づくりへの思い
イシハラスタイルの家づくりは、1回目の打ち合わせからお引き渡しまで、だいたい一年半です。ヒアリング完了までに3か月、プラン決定に2か月、コスト検討に2か月、設計に3か月、工期が8か月。 春に打ち合わせに来られて、年内に入居といったスケジュールを考えていたお客様からは驚かれたり、あきれられたりすることも。 しかし、イシハラスタイルが考え、実践している家づくりは、これが適切であり、 一緒に家づくりをされたお客様には結果的にご納得いただいていると思っています。
効率や時間を優先して丁寧さを失うことがないように妥協のないつくりを徹底することが理由の一つですが、 他にもたとえば、職人さんは気心が知れた腕と人柄に信頼がおける人にできるだけ一から十まで自分の手を動かしてもらうようにしていることも関係があります。 天候や段取りの都合、掛け持ちの現場もあり、工事の間が空くことがあります。 その時々で手順を変えたり職人が入れ替わりして間を埋めることが一般的ですが、 責任とやりがいとお客様への思いを貫いて現場を進めてもらうためには、 その人ができるすべてに関わってもらうのが良いと考えるからです。
対応エリアは、西尾市から車で30分から1時間くらいの範囲を目安にしています。 お客様と職人と現場とが、できるだけ近い距離にいるのが良いやり方だと考えるからです。
建築は繋がりから生まれるものだというのが、私の考えです。いい家を建てるのは誰かと問えば、それはいいお客様が建てるのです。 私たちがいい工務店になるには、いいお客様と出逢い、いい繋がりを持ちながら一緒に取り組むことが不可欠なのです。 そして、設計士と大工と職人、家具デザイナー、メーカー,作庭師たちがいい関係で繋がったプロ集団としてお客様のための家づくりに向かう。 そんな繋がりを大切にして、この一棟と真摯に向き合い、丁寧に丁寧に考え抜き、これでもかこれでもかとより良いものを探る。 お客様との対話にも、設計にも、工事にも、そして引き渡してからのおつきあいにも、すべてにおいて匠の精神を注ぎ、 家づくりに取り組みたいと考えています。
地元の工務店ということにこだわりを持つのも、地域と住まいと人との繋がりこそが、良い住まいづくりに欠かせないことだと考えるからです。
子どもの頃から古代の人の暮らし方や住まい方を想像することが好きでした。どうしてこの場所に暮らすことにしたのだろう。 雨風がしのぎやすいからなのか。食料が調達しやすいからなのか。
そんな興味がつづき、大学では自然の地形や都市の成り立ち、気象のことを学ぶ地理学を専修していました。 社会に出るときには、地域に根ざした町づくりができる仕事がないかと思い、不動産を扱う地元の建設会社に就職しました。 そこで「建築」と出会い、建築も街の要素なのだと気がつき、建築の世界に興味を持ち始めました。 建設会社では現場監督を経験し、その後海外留学の機会を得て、設計事務所にも勤め、大工の技術を身に付けたいと考え親方に弟子入りしました。 大工修行中に建築士の資格を取得し、イシハラスタイルを設立し、今に至っています。
あるとき、会社の特徴を言い表わすために、イシハラスタイルのことを「建築家大工」と呼んではどうかという提案を受けたことがあります。 しかし、私たちは建築家という言葉に違和感を覚えました。建築家の仕事が作品と呼ばれたりするのが違和感の一つだと感じます。
住まいは作品なんだろうか、と。では、イシハラスタイルは何だろうと自分に問いを向けたとき、「棟梁でありたい」と考えました。
イシハラスタイルは棟梁の志を持ち、地元の豊かさを大切にする工務店でありたいと考えています。 住まい手としっかり繋がって、設計、デザイン、現場、暮らし、建物、庭、環境が一体になった家づくりをめざしています。
石原 真 ishihara makoto
イシハラスタイル代表。1974 年生まれ。
県立西尾高等学校、愛知大学卒業。
一級建築士であり、大工でもある。

木の家に住みたい
木の家をおすすめする理由 その1
これは、私たちの実体験です。イシハラスタイルを興して最初の一棟は、自分たちの住まいでした。 まもなく築15 年となります。一般的には、いろいろなところに古さや傷みを感じ始める築年数ですが、 木の家はそれを感じさせません。新築当初よりも、木は日焼けしてあめ色に変わったり、 生活に伴う跡がそこかしこに増えていきます。しかし、古さや傷跡が欠点にならずに味わいに変わっていくのが木の魅力です。 木に限らず、時間とともに風合いを深めるのが自然素材の良さです。自然素材は裏切りません。傷にも変色にもシミにも愛着が持てます。年数を刻んだ証として暮らしになじみます。 必要なときにちょっとしたメンテナンスを施すことで、木の家は成長し、そして、記憶として刻まれていきます。 住む人と共に、ちょっとずつちょっとずつ表情を変えていきます。完成したときの状態をできるだけ長く保とうとするのではなく、 時の流れのまま自然のままと、おおらかな気持ちにさせてくれて、一緒に成長して、暮らしをやさしく包んでくれるのは木の家だからこそ。 木の家に暮らすこんな実体験が、皆様に木の家を自信を持っておすすめする理由です。
木の家をおすすめする理由 その2
想像してみてください。もし、自分が文鳥だったら、スズムシだったら。プラスチックの鳥かごや虫かごに入れられそだてられたくありません。 できれば、木やわらや紙の巣をつくっていただきたい。餌や水の容れ物もできれば陶器がいい。そんなふうに思いませんか。 掃除やお手入れがラクだから、安いから、という理由で棲家がつくられるのはさみしいものです。家(巣)は親がつくります。 子どもにとっては、その家が実家となります。どんな家(巣)をつくるのかは、親の重大な役目です。 豪華、高価な家でなく、正しい暮らし方に合った正しい住まいを一緒に考えましょう。
道具のような家
道具のような家。イシハラスタイルは、道具のような家をつくりたいと思います。そして、 道具のような家に共感してくれるお客様に出会いたいと願っています。たとえば職人の道具。大工の鑿(のみ)。意のままに正確に木を刻むために、大工は腕を磨き、刃を研ぎます。 使い込むと鋼鉄の刃もしだいに短くなっていき、ちんちくりんな鑿になります。こうなると、刃にも柄にも凄味が滲み出ます。 こういう道具を使いこなす大工は、きっと凄味のある仕事をします。鉋(かんな)や玄翁(げんのう)もしかりです。 手入れをしながら何十年も使い、その職人のかけがえのないパートナーになります。
衣服は暮らしの道具です。普段着や休日の服装など、TPO に縛られないときはどんなものを身に付けたいでしょうか。 藍染めのデニム生地。タンニンなめしの革。キャンバスのスニーカー。新しいうちはさまにならず、 着古して自分の体に馴染んでいくようなものを好ましく感じます。
キッチン道具にもいろいろあります。土鍋で炊くご飯。ぶ厚い鋳物の鍋でコトコト煮込む料理。 強火がガンガン使える鉄のフライパン。蒸籠(せいろ)を使った蒸し料理。こういう道具には、 アレコレの便利さはありませんが、一芸に秀でたところがあります。ちゃんと使って、ちゃんと手間をかけると、 味わいのある料理が作れるようになるのだと思います。
道具は人の手の延長で使うもの、と言われます。人に代わって仕事をこなす機械との違いは、そこです。
道具のような家というのは、住まいとしての機能性をただ満たしているということではなく、 住む人の身体や気持ちとつながった住みやすさをそなえているということです。 住む人と親密になれる住まいであり、住み続けていく中で愛着が湧き、ますますいい家になっていく。 そんな家だと考えています。
職人が道具を自ら手入れするように、気に入りの洋服は手洗いしたり汚れがついたらシミ抜きして着つづけるように、 道具のような家は住む人が自分で手入れできるという意味もあります。 手入れは必要です。その手入れが大変なことではなく、誰にでもできる比較的簡単なことで、 楽しいと感じられるようなメンテナンスファンな家を住む人に合わせてつくりたいと思います。
こまめに手入れをして何十年も使うことも考えられるし、5年10年といった比較的短い期間で交換することを見越して選択する材料もあります。 たとえばウッドデッキの板材は、南洋材を使ってマメに手入れをして30 年以上持たせることもできるし、お手軽に地元の桧材を採用して ガンガン使いこなし、15 年も使ったら「ありがとう」という気持ちで新しい材に張り替える、という住まい方もあります。
外壁には昔ながらの杉板をおすすめすることがよくあります。いずれ灰色に枯れていく杉の経年変化は好みの分かれるところかもしれませんが、 風土に、生活に馴染んでいく様は、とても素晴らしいものだと思います。私自身、大工を経験したときに、築40~50年の杉板張りの外壁修繕を何軒も行いました。 どこの大工さんが建てた家か分からなくても、建ててから何十年も経っていても、杉板は容易に入手できるし、初歩的な大工技術で簡単に修繕できます。 品番がついた工業製品はやがて廃番になることもありますが、杉板に廃番はありません。部分的に張り替えると、板の新旧で色の差がでますが、 これはこれでいい眺めだと思います。家にちゃんと手を入れている、そんな雰囲気が醸し出されます。そして、板の色の差は時間と共に薄れていき、ちゃんと馴染みます。
適材適所の考え方や、理にかなったシンプルさが、道具のような家に通じる発想ともいえます。 なんでもかんでもスペックを高めるのではなく、持たせるところはしっかりと持たせて、 傷みやすいところは修繕のしやすさを備えておくことで、いつまでも嬉しい気持ちで住み続けられる家になります。
どんな道具を選ぶのか使い手によってそれぞれ違うように、家という道具も住む人の暮らし方や考えによって十人十色です。 お客様に合った道具のような家を一緒に考えます。

好きを大切に暮らす
大切なことは、日常の豊かさ、身近な幸せ、日々の嬉しい時間。インテリアのプランニングやコーディネートは、形ではなく一人ひとりの暮らしと住まいをどうむすびつけるかということです。打ち合わせでは、家事や育児のことで奥様と会話がはずむことがよくあります。 働く主婦として、簡素化できるとことは省き、楽しめるところは遊び心を持って。 話をたくさんして、住まい手の趣味や好きなものを取り込めるようにしています。 そうやって話し合いをしていくことで、家を好きになってもらいたいと考えています。 家が好きになれば家事も楽しくなるはずです。
「できるだけ収納はたくさん欲しい」、「床面積は最低でも40 坪以上」と、家づくりの要望のなかでよく耳にする台詞です。 もちろん、収納が多ければ片付けも楽ですし、延べ床が広ければ、ゆとりをもって暮らすことができます。
しかし、必ずしもそうした住まいにしなければ、快適に過ごせないわけではありません。無駄な廊下などを省き、 心地よい居場所をいろいろなところにつくることで、小さくてもゆたかな気持ちで暮らすことのできる住まいにすることは可能です。 お客様の「好きな家」を実現するために、たとえばペットとの暮らし方なども、私たちは綿密に考えます。
作庭やグリーンの提案も積極的に行っています。自然や植物とふれあい、季節の流れを暮らしの中で感じることで、 日々の暮らしは楽しく豊かになります。子供の感性も間違いなく高まります。
若葉が萌え、花が咲き、実がなり、野鳥が集まり、お天気や季節によってさまざまな表情を見せてくれる。 お話をじっくり聞かせていただき、お客様の考えや思いに適ったプランニングをめざします。
家づくりはお客様のプライベートにぐっと入り込んでお話しします。信頼していただき、 人間関係を築くことも家づくりに携わる上で大事な使命だと考えています。 お引き渡し後も、末長くお付き合いいただけることを心がけていきます。
石原 智葉 ishihara tomoyo
一級建築士の資格を持つインテリアコーディネーター。
キッチンスペシャリストの資格も持ったインテリアのプロであり、
同時に一児の子をもつ主婦でもある。

無いものはつくり出す
住宅は工業製品に類するものですが、一品生産の注文住宅を工業製品といってしまうことには違和感を覚えます。実際、既製品や工業製品が住宅のパーツとなる部分は少なくありません。家電や家具はそうですし、 外装材、内装材にもメーカー製品を使います。それは悪いことではまったくありませんが、中には一般的には普通とされているものに違和感を感じるものがあります。 とくに、建物本体に取り付けるものとして、住宅設備、建具、造作家具などがそうです。
道具のような家、「好き」を大切に暮らすお家を実現するために、こうした違和感を覚えるものに対しては、 常識を見直しながらイシハラスタイルの家はこうなんだ、というスタンダードを考え続け、 思いを実現するための取り組みを具体的に推し進めています。
股旅社中という会に参加していることもその一つです。家具デザイナーや家具メーカーとチームを組んで、 オリジナルの家具・建具・道具づくりに取り組んでいます。この活動は、デザイナーにデザインを依頼するのではなく、 「こういうコトを実現したい」という目的を共有し、それに向かって「一緒に考え」、「一緒に手を動かし」、「現場で確かめ改善を重ねる」、という取り組みです。
単に新しいモノを生み出すことが狙いではなく、イシハラスタイルのお家に住みたいと思ってくださる方の考えを受け止め、 それを実現するためにデザイナーや家具メーカーとともに考え方や取り組み方からデザインし、目的をかなえるのに相応しい既製品が世の中に無ければ、 それを自力でつくり出そうということです。
いま、イシハラスタイルが標準としている家づくりの仕様は、股旅社中活動を通して培ってきた現在の到達点です。 目に見えるものでいえば、「タフなキッチン」や「タフな浴室」はその成果の現れです。その活動から直接的につくり出したものでない項目も、 その仕様に至ったのは何が最良なのかを追求してきた成果です。世の中になかった家具をつくり出し、常識と思ってきた造作をそぎ落とし、過不足ないと考えてきた材料を見直す。
それは、他社と差別化するためのオリジナル開発でなく、当たり前と思ってきたことの中にある違和感に気づき、 それをどう改善するかに取り組むことです。一番の問題は、違和感に気づくこと。
違和感に気づくために、イシハラスタイルのお家に住みたいと思ってくださるお客様の声に、一生懸命耳を傾け本質を読み解くことだと考えます。